― 認知行動療法とマインドフルネスで心を整える ―
◆「休職=ただ休む」ではない
休職をすると、多くの人がこう感じます。
「本当に休んでいていいのかな?」
「動かなきゃと思うけど、体も心も重い」
「このまま社会に戻れるのだろうか…」
でも、忘れないでください。
休職は“逃げ”ではなく、“心の治療と再設計の時間”です。
壊れかけたエンジンを無理に動かすのではなく、
「一度止まって整える」ことが、次に進むための最短ルート。
焦る必要はありません。
休むことも、回復の一部です。
この記事では、うつ病・適応障害・統合失調症・発達障害の方が
休職中に「どう過ごせば回復につながるのか」を、
臨床心理士の立場から認知行動療法(CBT)とマインドフルネスの視点で解説します。
◆うつ病の休職中の過ごし方
●認知行動療法(CBT)の視点
うつ病の特徴の一つは、「自分を責める思考」にとらわれやすくなること。
「自分は役に立たない」
「何をしてもダメだ」
これらは“自動思考”と呼ばれます。
気づかぬうちに頭の中を支配し、心を沈ませてしまうのです。
例えば・・・私たちは出来事が起きた瞬間に、反射的に「心の中のつぶやき」が浮かびます。
たとえば、上司に「あとで話がある」と言われて「怒られるかも」と思う――この瞬間の考えが自動思考です。
この思考の内容によって、気分や行動が変わります。
だから、落ち込みや不安を感じたときは「今どんな考えが浮かんだか?」に気づくことが大切です。
まずは、その思考を書き出してみましょう。
例:
「自分は役立たずだ」 → 「今は休養中。治ればまた働ける」
書き出すことで、
“思考”という思い込みと“現実”の現状を分けて見ることができます。
これが思考の整理=CBTの第一歩です。
「何をしてもダメだ」 → 「休職前はできていたことあったじゃないか
「自分は無力だ」 → 「会社でいろいろやっていたじゃないか」
続けるうちに、心が少しずつ軽くなっていきます。
自分の中で思い込んでしまう思考と、ほんとうにそうなんだろうか?と違う視点を持つことで、自分を責めてしまう悪循環から解放していきましょう。
専門用語でいうと「反芻」というものがあります。自宅で自分で自責の念に駆られる毎日ですと余計に自分自身が苦しくなっていきます。
いまは回復に務めてください。
●マインドフルネスの視点
うつ病では、過去の後悔や未来の不安に囚われやすい状態が続きます。
今現在 休職して休んでいるのに、過去の後悔や、将来の心配について、まるでバーチャルリアリティであるかのように、ネガティブな世界にダイブしてしまいます。
そんな時こそ、「今この瞬間」に戻る練習をしてみましょう。
マインドフルネスについて簡単な説明はこちらから
呼吸に意識を向けるだけでも構いません。
「吸っている」
「吐いている」
心でつぶやきながら、呼吸を感じてみてください。
3分でも続けると、不思議と心が落ち着いていきます。
焦点が“今”に戻ることで、思考の渦から抜け出せるのです。
◆適応障害の休職中の過ごし方
●認知行動療法の視点
適応障害は、**「特定のストレス」**が引き金になります。
職場の人間関係、環境の変化、プレッシャーなどが重なり、
心が悲鳴を上げてしまうのです。
CBTでは、次のように「状況・感情・思考」を整理します。
例:
- 状況:「上司に強い口調で注意された」
- 感情:「不安・悲しみ・無力感」
- 思考:「やっぱり自分は向いていない」
紙に書くことで、「事実」と「思い込み」が分離されます。
気づけば、「あの時の自分は責めすぎていたな」と思える瞬間が来るでしょう。
また、適応障害であるのであれば、職場を変えてみるという方法もあるでしょう。その環境に適応しづらいという視点もあるかもしれません。選択肢は多く持っていた方がよいです。
●マインドフルネスの視点
適応障害の回復には、“ストレス源から離れて自分を取り戻す時間”が欠かせません。
おすすめは「五感マインドフルネス」。
散歩をして、風の匂いを感じてみましょう。
食事の味や香りに意識を向けましょう。
鳥の声や光の変化に気づいてみましょう。
今ここに起きていないストレスについて考えてしまうと、それはそれで、心が疲弊していきます。そういう脳の使い方が現代の脳疲労。ストレスをいつの間にか自分自身で作り出しているのです。
そこから脱却するために、今、ここで、私は、ここにいて、今は安全である感覚を取り戻すことも大事です。確かに将来の心配というのは誰にでもありますが、そこにばかり注意が向いてしまうと休める時も休めません。
脳や精神を整えるためにもマインドフルネスを活用しましょう。
今この瞬間に戻る体験を繰り返すことで、
心は「再び自分を取り戻す力」を取り戻していきます。
◆統合失調症の休職中の過ごし方
●認知行動療法の視点
統合失調症では、幻覚や妄想など現実感覚がゆらぐ時期があります。
「誰かに見られている気がする」「陰で話されている」「胴長短足といわれた」「咳払いされて中傷された」「好奇的な目で見られた」「急に怒鳴られる声がした」と感じても、
それが“現実”か“思考”かがわかりにくくなることがあります。
だって、自分の中の体感ではそう聞こえるんだもん。って。
CBTでは、主治医や心理士と一緒に、
「証拠はある?」「別の可能性は?」「それがあなたにどのような意味があるのか」「悪意はどう感じられるのか」「それは相手が放っているだけなのか」と、
信頼関係のある中で、ゆっくりと現実検討を行います。
安心できる場では誹謗中傷にさらされるわけではありません。
そのような安心感をはぐくみつつ、現実の安心感を実感して、あなたに危害を加えることは今は起こっていないという安全基地を形成していくことが大事なことです。
焦らず、**“事実を一緒に見つめる練習”**をすることで、
少しずつ「安心して現実に戻る感覚」が育まれます。
●マインドフルネスの視点
症状を「なくそう」と力むほど、苦しさは増します。
大切なのは、「症状を観察して、流す」こと。
「いま幻聴があるな」
「心がざわついているな」
そう気づいて、ただ観察する。
否定も肯定もせず、“あるがまま”を受け入れる。
それが、心のしなやかさを育てます。
諸行無常。非常につらい思いもありますが、それも変容していきます。私たちは、気持ちが沈んだとき「ずっとこのままかも」と思いがちですが、感情も体の感覚も必ず移り変わります。
「今のつらさも変化の途中」と気づくだけで、少し心が軽くなります。
◆発達障害(ASD・ADHDなど)の休職中の過ごし方
●認知行動療法の視点
発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)を持つ人は、
「努力しても同じミスを繰り返す」「空気が読めないと言われる」
といった経験から、自己否定のスパイラルに陥りがちです。
CBTでは、できないことを責めるのではなく、
「どうすればできるか」「よりよく生きるためには」を探します。
今はICT技術が発展していたり、勤務形態や仕事の内容もリモート化していたりして、様々な働き方や、約束の守り方もあります。タスク管理アプリも充実しています。
例:
- 「集中力が続かない」→「25分だけ集中+5分休憩」
- 「整理が苦手」→「片づけのルールを1つ決める」
- 「忘れやすい」→「メモとアラームを活用する」
大切なのは、“特性を変える”のではなく、
**“自分の特性に合わせて環境を整える”**こと。
●マインドフルネスの視点
発達障害の方は、感覚過敏や刺激への反応が強い傾向があります。
マインドフルネスでは、
それを「コントロール」ではなく「観察」として扱います。
「音が気になるな」→「今、音が聞こえている」
「人の視線が気になる」→「そう感じている自分がいる」
この“気づき”を積み重ねることで、
刺激や不安との距離が少しずつ取れるようになります。
◆誰にでもできるマインドフルネス3選
① 呼吸瞑想
- 背筋を伸ばし、呼吸に意識を向ける
- 「吸っている」「吐いている」と心でつぶやく
- 雑念に気づいたら、呼吸に戻る
1日3分。心の筋トレです。
② 五感マインドフルネス
- 見る:空の色、木の葉の動き
- 聞く:生活音や遠くの車の音
- 感じる:足裏の感触、風の温度
- 嗅ぐ:お茶やシャンプーの香り
- 味わう:食べ物の温度や舌触り
“今ここ”の体験を丁寧に味わうことが、心の安定を生みます。
③ ボディスキャン
- 足先から頭まで体の感覚を順に観察する
- 「重い」「温かい」と評価せず感じる
思考のループが静まり、眠りの質も改善します。
◆休職期間に共通して大切な3つのこと
- 生活リズムを整える
→ 起床・食事・日光浴。この3つが心身のリズムを支えます。 - 小さな行動を積み重ねる
→ 散歩5分、日記1行、呼吸3回。これで十分です。可能であれば、気分良く作業できることがあるとさらによいかもしれません。作業療法・・・食事の準備や片付け、創作活動(絵、手芸、園芸、工作など)やってみて気分的に良かったなと思える行動を続けてみてください。 - 自分を責めない
→ 「休むのも治療」。そう考えることで、罪悪感は和らぎます。一旦は仕事環境からの距離をとることも必要な時間であります。どうしても責めてしまうといったこともあるかもしれません。そういったときは素直に他者に頼りましょう。休職の診断書を発行してくれたドクター、カウンセリング、リワークデイケア、デイケアに通所してプロの専門家に相談してみるのもいいと思います。独の世界だと、見えない景色が、専門家や他者視点との触発で見え方が変わることがあります。
◆まとめ:休職は“止まる”時間ではなく、“整える”時間
- うつ病:思考を整理し、呼吸で「今」に戻る
- 適応障害:ストレス構造を見直し、感覚を取り戻す
- 統合失調症:現実検討を支え、安心を積み重ねる
- 発達障害:特性を理解し、環境を工夫する
- 共通:生活リズム・小さな行動・自己受容
休職は終わりではなく、「再スタートの準備期間」です。
今日ここまで読んだあなたは、すでに回復の第一歩を踏み出しています。
参考文献
- Beck, J.S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond
- Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever You Go, There You Are
- Hayes, S.C. (2011). Mindfulness and Acceptance
- 厚生労働省「こころの耳」メンタルヘルス・ポータルサイト
- 日本うつ病学会・日本認知行動療法学会 ガイドライン
- 日本発達障害ネットワーク(JDDnet)「発達障害の理解と支援」
今日のあなたにできる“小さな一歩”
- 深呼吸を3回してみる
- 光の差す方を見てみる
- 苦手なことを「どうすればできるか」で考えてみる
💬 コメント欄で、あなたの「一歩」を教えてください。
その言葉が、誰かの心を照らす灯りになるかもしれません。

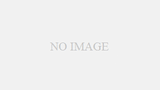
コメント